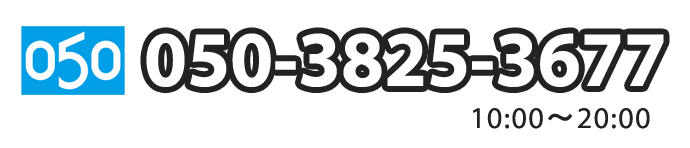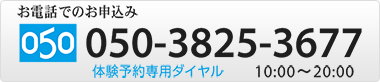先日、ワンズウィルミュージックスクールのTwitter「ボーカル請負人」で、
とつぶたいたところ思わぬ反響がありました。
世の中の音程が綺麗にそろいすぎているCDに、皆さんも違和感を覚え、もういいかげん飽き飽きしてきているのではないかと勝手に推測します。
確かに、歌が上手く歌えなかったり、ニュアンスや響きが良いんだけどもこの箇所だけはどうしてもピッチが良くなかった、という時などは音程修正は必要だったりします。
音程直しは必要だが、その直し方に問題がある。
音程だけをピタッと合わせるのはそんなに手間がかかる作業ではありません。
例えばAuto Tuneのグラフィカルモードにてノートオブジェクト(波形が四角い枠で囲まれている部分)を使えば、修正したい音程に自動で合わせてくれます。

四角い枠で囲んだ部分がノートオブジェクト機能で、ピッチ補正された歌の波形図
ノートオブジェクトを使うと音程は簡単にピッタリ直るのですが、上のピッチ補正をした歌の波形図をご覧になれば分かると思いますが、波形が元音とかなり変わってしまい、当然声質も相当変化します。また音質的にもかなり劣化してしまうんですね。
ましてやボーカリストの”節回しやしゃくり”なども完全に崩れてしまうので、違和感のある機械的な声になってしまうのです。大幅に音程を動かすと、皆さんも聞いた事があるであろうシンセサイザーみないな声質になってしまいます。
ですので私はピッチ修正をする場合、決してこのノートオブジェクトは使いません。
とても手間はかかるのですが、キチンと歌を聞きながら、入りの音・語尾・歌中など、元の波形を生かすところは生かし、ポイントで悪い部分だけをピッチ修正するようにしています。
ある意味、入りの音が高かったり低かったり、語尾が落ちていたりしても、聞いて余程ひどくなければ、それはボーカリストの歌ったものを生かすように直します。
実はこうする事で、歌の音程は自然に直ります。
しかしこれらは、波形を一つ一つ切ったりと非常に時間と手間がかかるし、歌を理解していないと難しい作業なんですね。
ただ残念な事に、丁寧に音程が直されている作品は少ないと言っても過言でないでしょう。簡単に、しかもピッタリ音程が直る方法(上の図のような線を引くような方法)で歌がいじられているCDはとても多いのが現状です。
歌は音程が全てピッタリ合っている必要はないのです。
歌をピッチ修正するのであれば、ボーカリストの表情や揺れ具合をいかに音楽的に自然に直すかが鍵になります。
例えばマイナー調の曲などはフラット気味の方が音楽的に心地良かったりする事も多いですし、アップテンポの明るいロックの曲などは、歌の入りは若干シャープしているくらいの方が、勢いが出たりします。
その若干合っていない部分も、聞いてヒューマンかつ音楽的であったら、あまりいじらない事が大切なんですね。
実はその方が”ビシッと音程を合わせている歌”よりも人間が歌った歌として、気持ちよくバックの演奏と馴染むのです。
歌の音程は流れで聞いて違和感がなかったらそれでよしです。
その音だけを聞いていると低かったり、高かったり感じたとしても、オケとの兼ね合い(バックの楽器との聞こえ具合)や、前のフレーズからの流れで聞いて、どう歌が聞こえるか?が大切なんですね。
また、ある意味音程が一定でない楽器(Stringsや管楽器)が中心のオケの場合、歌だけが正確な音程を奏でていると、ハーモニー的に心地良く聞こえない場合もあります。
人間の声は揺れるものです。キーボードの鍵盤を弾いた音のように、音程がピッタリには行かないのが当然です。歌は楽器ではないのです。
この世の中、音程がピッタリ合いすぎていて、人間味のない、やや面白みに欠けている歌が多いような気がします。そしてリスナーも音楽制作者もボーカリストも「完璧な音程」に慣れすぎているんだと思います。
もうそろそろ、その違和感に気づいた方がいいかもしれない時期なのではないでしょうか?